【日本の自動車業界 踏んだり蹴ったり、トランプ関税で輸出減少・輸入増加】
欧州の大手自動車メーカーがEVの開発遅れとトランプ関税の影響で売り先を変えざるを得ず、日本で価格を下げて売り出している。ここにきて円安も一段落、日本のメーカーにとっては踏んだり蹴ったりの状況だ。日本の自動車業界、減速するで。
【内閣府 遂に消費者心理「弱含んでいる」に下方修正、5カ月連続低下でやっと判断】
内閣府が発表した4月の消費動向調査で、消費者態度指数が前月より2.9ポイント低い31.2%と5カ月連続で低下。これを受けて基準判断を「弱含んでいる」と、3カ月ぶりに下方修正した。今後も「物価が上昇する」と回答した人は9割を超え、米国の関税措置の影響もあり、先行きは不透明。消費者マインドを押し下げている可能性が高い。
【「すき家」異物混入で3日間休業、客離れが続き全店売上高が20%減少、当たり前やで】
24時間営業を売りにする牛丼チェーン「すき家」で再三にわたり異物混入が発覚し、全店を3日間休業して清掃を実施。さらに客離れも起こり、全店売上が20%減少したと発表。適切な対応で拡大は防げそうだが、下手すれば営業停止や復活困難な重大問題に発展しかねない。人手不足にもかかわらず、無理な営業時間や労働は事故の元。肝に銘じるべきだ。
【不公平で問題ばかりのふるさと納税、2023年に1兆円を突破・4年連続で過去最高更新】
ある自治体が米に補助金をつけて返礼品として大量に税金を集めるなど、産地偽装も絶えないふるさと納税が4年連続で記録を更新。昨年から米が高騰し、米の産地は返礼品で潤っている。問題となった過大なポイント付与は2025年秋に廃止予定だが、その影響は不明。人気返礼品がない自治体は気の毒だ。本来の税収・交付金の目的から外れ、特定事業者だけが儲かる構図は主旨に反しており、可笑しいと言わざるを得ない。
【遂に鰻も「メス」が人気に。ふっくら肉厚が魅力、人間の心理は希少性に対価を支払う】
鰻丼が3000円、うな重が5000円といった価格が一般的となった昨今、名店では1万円以上のコースも登場。高ければ高いほど、希少になればなるほど食べたくなるのが人間の心理。牛肉では「メス」の方が柔らかくて美味しいと人気を集めており、高級焼肉店でも売りにしている。遂に鰻でも「メス」がふっくら肉厚で美味しいと話題になり、名店では別途訴求を開始。遠方から訪れる人も増えている。このグルメブーム、いつまで続くのだろうか。
【年金だけでは生活苦、働くシニア70歳以上の就業者540万人・2014年比で7割増】
働くシニアが増加している。年金受給開始が65歳以上に引き上げられたことや、人手不足による雇用の活発化が背景にあるが、本音は物価高の中で年金だけでは暮らせないということではないか。年金受給年齢の引き上げにより、就業者に占める65歳以上の割合は全業種平均で14%、介護や建設業では17%に達する。60歳以上の再雇用枠を広げる企業も増加。シニア就労が進めば社会保障費の抑制にもつながるが、高齢者が死ぬまで働かないといけない日本の社会保障制度とは…。
【東京のオフィス賃料 17年ぶりに高水準、人材確保で移転活発、採用状況まったく違う】
東京都内の既存ビルの賃料が前年比で5%上昇し、2008年のリーマンショック前以来17年ぶりの高水準となった。人材確保を有利に進めようと、利便性の高いオフィスに移転する企業が増加。主要ターミナルの立地が変化し、人々は利便性を求めて市街地に移り住む傾向が強く、それに合わせて職場も移動する時代となった。弊社も人材採用を目的に2016年に大阪市西淀川区から大阪北区(駅前)へ移転。応募状況も大きく変わり、良い人材を確保しやすくなり、離職率も減少した。一石二鳥とはこのこと。今後は休日日数、残業の有無、勤務時間や働く場所も、人材確保に影響する。
【2025年4月1日時点 子供の数、外国人含め1366万人 44年連続減少・過去最低を更新】
政府の対策は全く役に立たず、15歳までの子供の数が外国人を含めて1366万人となり、44年連続で減少。過去最低を更新した。また、総人口に占める割合も11.1%と減少。年代別では年齢が下がるほど人数が少なくなる傾向にある。都道府県別では、子供の割合が最も高いのは沖縄県で15.8%、次いで滋賀県と佐賀県が12.7%、熊本県が12.6%と続いた。一方、最も低かったのは秋田県の8.8%、青森県9.8%、北海道9.9%。このままでは、国の維持が危ぶまれるのではないか。
【外食の回復は二極化 2人以上世帯では支出過去最高・単身世帯はコロナ前に届かず 居酒屋は7割減】
総務省の家計調査によると、2024年度の一般外食費は前年より9%増の17万999円となり、コロナ前(16万6712円)を上回り過去最高となった。ただし、これは消費が増えたというより、実際に米などを多く使う店舗での値上げによって外食費がかさ増しされた結果といえる。物価変動を除いた実質ベースでは、コロナ前の93%の水準にとどまる。ファーストフードが好調で、食堂・レストラン専門店も9割台まで回復。共働き世帯の増加により、自炊が減少していると見られる。一方、パブやレストラン、居酒屋などは2019年度比で3分の2の水準にとどまり、依然として苦戦している。そらそうやろ。
【フジッコ 節約志向と健康ブームで豆佃煮・昆布佃煮がバカ売れ 2028年営業利益2.7倍に】
節約志向の高まりで「ご飯の友」が売れている。大豆の佃煮や昆布の佃煮を主力とするフジッコは、2028年3月期の営業利益が前期比2.7倍の30億円以上になるとの見通しを発表した。
【ゲオホールディングス 中古衣料・雑貨・スマホなどリユース店を拡大 純利益21%増見込み】
物価高を背景に節約志向が高まる中、ゲオホールディングスはリユース店「セカンドストリート」を国内外で積極出店。中古スマホを取り扱う「ゲオモバイル」も店舗数を拡大し、レンタル店舗の損失を補うかたちで、2026年3月期は純利益21%増を見込むと発表した。
【パナソニック 1万人削減を発表 早期退職などで2027年3月までに実施 総社員の約4%】
パナソニックグループの従業員は世界で約22万8000人。今回の削減はその4%に相当する。パナソニックHD本体や傘下の各事業会社は、人事や経理などの間接部門が重複しており、以前から投資家などから統合が求められていた。今回の再編により、赤字事業の撤退・統合も進め、2027年3月までに1220億円の損益改善効果を見込む。家電業界、厳しい。
【いくらでも増える 国の借金1323兆円 9年連続で過去最高 誰も止めない】
財務省は、国債・借入金・政府短期証券を合計した「国の借金」が2024年度末時点で1323兆7155億円になったと発表。9年連続で過去最高を更新した。政府は支出を税収で賄いきれず、借金が膨らみ続けている。もはや返済できる金額ではない。
【4月倒産件数 近畿で前年比20%増 過去10年で最多 原材料高騰と人手不足が主因】
東京商工リサーチが5月9日に発表した2025年4月の近畿2府4県における倒産件数は、前年同月比で20%増。業種別では建設業が最多、サービス業も4%増加した。共に原材料の高騰や人手不足が要因とみられる。平均負債額は8700万円と比較的小規模で、全国的にも小口倒産が増加している。
【金利上昇で銀行各社が好決算 貸出残高が過去最高の銀行が増加】
日銀のマイナス金利政策が終了し「金利のある時代」へと転じる中、銀行各社は貸出残高の増加とともに好決算を発表する動きが目立っている。住宅やマンション価格の上昇もあり、今後も貸出残高は増える見通し。ただし、その分金利も上昇し、破綻リスクも高まる構造になっている。

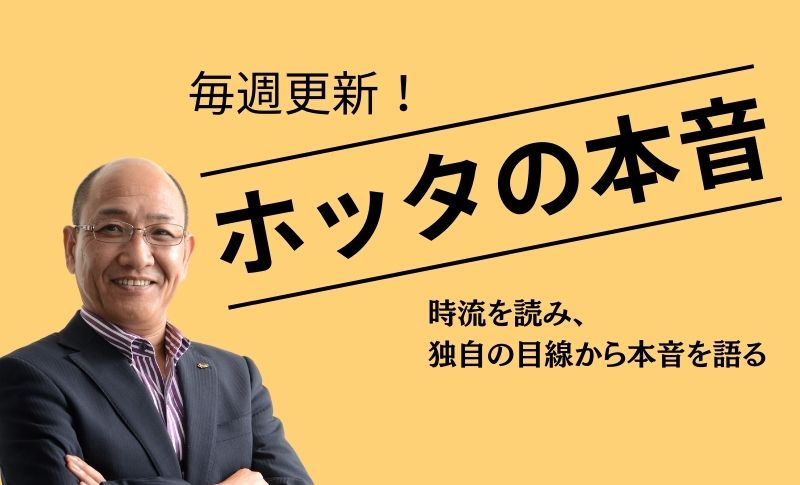
コメント